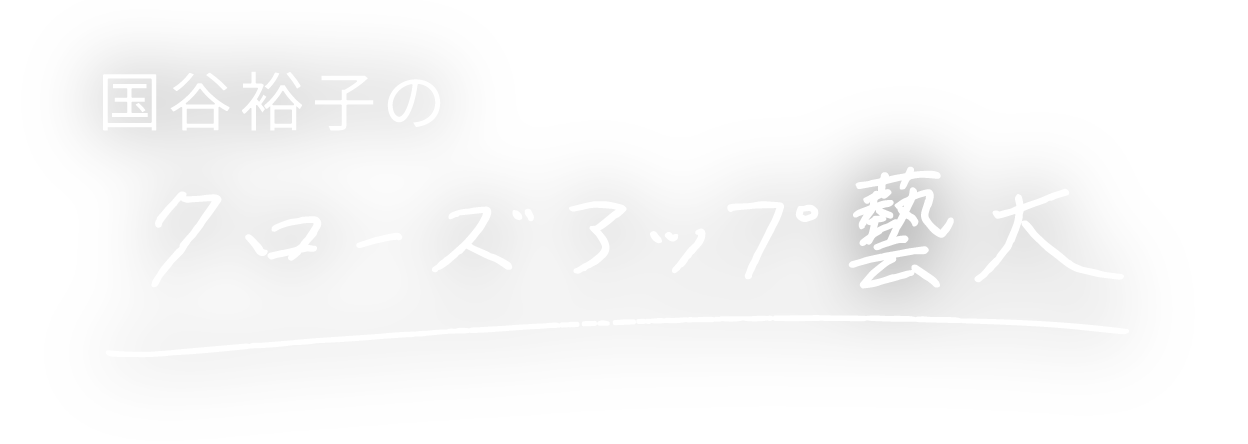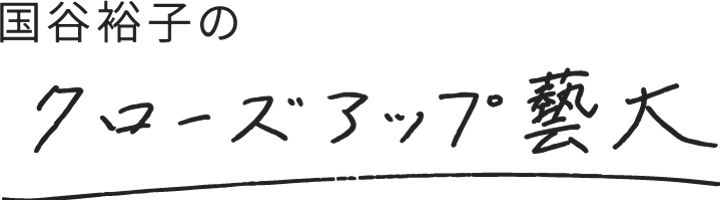第二十一回 今村有策 大学院美術研究科グローバルアートプラクティス専攻教授/副学長(国際連携担当)
クローズアップ藝大では、国谷裕子理事による教授たちへのインタビューを通じ、藝大をより深く掘り下げていきます。万博体育APP官方网_万博体育manbetx3.0の唯一無二を知り、読者とともに様々にそれぞれに思いを巡らすジャーナリズム。不定期でお届けしています。
>> 過去の「クローズアップ藝大」 |
|---|
第二十一回は、大学院美術研究科グローバルアートプラクティス専攻教授の今村有策先生です。東京都の文化政策に長年携わり、2018年より本学に赴任。国際連携担当の副学長、そしてグローバルサポートセンターのセンター長としても世界中を飛び回っています。2024年10月、国際交流棟のコミュニティサロンにてお話を伺いました。
【はじめに】
「三回連続ナイトフライトだったので足がもうガクガクです」と話し始められた今村先生は藝大の国際連携担当の副学長。上海から羽田、その日のうちに羽田からジャカルタ、そしてまたジャカルタから羽田と活発に飛び回っている様子を伝えてくれました。
藝大の学生が海外の大学と交流する機会を増やしたり、各国から藝大に学生や優れた専門家を迎え入れたり、他の大学と同様、藝大にとっても国際化は重要な戦略になっています。
国際化の重要性について今村先生が繰り返し強調されたのは、国や文化圏の異なる人々と身近にふれあうことができる環境があってこそ、豊かな人が育つ土壌が生まれるということでした。
国谷大学美術館では「黄土水とその時代— 台湾初の洋風彫刻家と20世紀初頭の東京美術学校(会期:2024年9月6日- 10月20日)」展が開催されていますね。8月には「東京藝術大学と中国人留学生?李叔同から現代まで?」展もありました。藝大は東京美術学校の時代から留学生を受け入れてきました。現在も学生のうち約10%が外国人留学生です。
今村さんは以前、藝大には本当は様々な文化に触れられる土壌があるのだけれど、なかなかそれをいかせてないとおっしゃっています。
今村現在も古くからの留学制度に頼っているので、ただ外国から学生が来て、帰るだけになっているんですよね。外国と日本、双方の学生が一緒に何かプロジェクトをやるとか、教員同士が交流するといったことに、なかなか発展していないのが現状です。
中国から日本に留学して、帰国してから大学などで教育者になった方がたくさんいるので、その方たちが退官される前に、次の世代につなごうとしています。先日も上海と北京に行ってきました。その前は杭州にも行きました。小沢剛さん(先端芸術表現科教授)も一緒に。
国谷小沢先生も国内外でいろいろな展示をなさっています。
今村小沢さんとは2018年から毎年、学生を連れてアジアを回っています。ベトナムのホーチミンから始めて、タイのバンコク、インドネシアのジャカルタに行きました。そういうふうに積み重ねてきて、バンコクのシラパコーン大学が僕らの活動を理解してくれて、大学間の交流が始まりました。
グローバルアートプラクティス(GAP)専攻の柱となる授業はロンドンとパリとの授業で、僕が赴任した2018年当時はアジアとの交流があまりなかったんです。 GAPはスーパーグローバルユニバーシティーの枠組みで2016年に新しく設置された専攻なんですけれど、そんなグローバルな学びの場所なのに、なんで今の時代になんでアジアをやらないんだ!って言って。

国谷藝大はShared Campus*にも参加しています。
| Shared Campus…欧州、アジア7つの芸術系大学、芸術系学科を持つ総合大学が共同で立ち上げた国際的な教育形態と研究ネットワークのための協力プラットフォーム。地球規模の課題解決にむけて、国境を越えた学術的交流を生み出すことを目的に設立された。 |
今村 日比野学長に、当時は学部長だったんですけれど、こういう国際交流をやらなきゃだめなんですって訴えて、それで2022年から参加することになりました。
国際交流ということでは、藝大は各国の芸術系教育機関のトップを招いてサミットをやったこともありました。「藝大アーツ?サミット2012」は僕が東京都の参与のときで、東京都のアジアのネットワーク推進を担当していたので、オブザーバーとして参加したんです。「五大陸アーツサミット2018」のときは、僕はまだ藝大に赴任していなかったんですけど呼んでいただいて、南カリフォルニア大学やコロンビア大学、ベルリン芸術大学などの方々と意見交換をしました。
僕がその時に感じたのは、大きな議論をすることも重要ですが、まずは学生1人1人が成果を上げていけるような環境を作れば、次は議論ができるだろうと。副学長になって今年で3年目ですけれど、2年間はコツコツと実績を作ってきたので、3年目は何か大きなフレーミング、ビジョンみたいなものを作ろうと思っているところです。国谷今村さんはよく、土壌が大事だと強調されていますが。
今村やはり行政とか大学とかって、立派な見栄えのする花が欲しい。僕がよく比喩で使うのが、花と花瓶です。80年代90年代はお金があったので、でっかい花瓶を作って切り花を持ってきて飾っていた。花瓶は美術館とか劇場ですね。だけどバブルが終わって切り花を持ってくることができなくなり、気が付くと空の花瓶が残っていた。じゃあ、まずは土を耕して豊かにしようと。豊かな土壌に議論の種が撒かれることによって芽は自然に伸びていくわけですから。
大きな文脈の中で考える

国谷今村さんは学生時代は建築を学び、卒業後は竹中工務店に就職し建築家としてのキャリアをスタートして、その後、磯崎新さんのアトリエで10年ぐらい勤めました。建築を専門にされてきた方がどうして、今行われているようなグローバルな教育活動に携わるようになったのでしょうか。
今村竹中工務店にいたのは2年ですけれども、いろいろな現場を見たり積算をやったり、何でもやっていました。磯崎さんのところでは、東京都庁舎の設計のコンペがしょっぱなでした。コンペは負けてしまったんですけど。
磯崎さんは哲学にも現代アートにも詳しいし、建築を建築だけの狭い世界で見るのではなくて、一つの文化として、あるいは文明として見るという目を持っていらっしゃって。都市の歴史的な成り立ち、社会の成り立ち、なおかつそこにおける政治のあり方みたいな文脈を見ていました。設計のときは、今そこに建築として何かを挿入することによって、軸がずれたり、何かが起爆されたり、そこに人が集まるようになるかということをいつも考えていました。
磯崎さんのアトリエでは、そういう文脈をまずしっかり考えるという訓練をさせてもらいました。地方自治体のプロジェクトや大学のキャンパス計画もありましたね。一緒にリサーチしたり判断をしたりしながらデザイン化して。建築はただ建物を設計するわけではなくて、場を作っていくことなんだと思いました。
磯崎さんのところにいたときに、文化庁の在外研修という制度でコロンビア大学の客員研究員になり、ニューヨークに滞在しました。そこで荒川修作さんに出会った。
国谷1990年ぐらいですか?
今村ニューヨークには1991年から4年いました。実は磯崎さんも荒川さんの大親友で。荒川さんも世界の在り方とか芸術の役割みたいなことを、毎日議論していました。
世界の名だたる哲学者とかアーティストが、荒川さんと議論をしに毎晩のように訪ねてくるんです。僕も仕事が終わると、荒川さんのお宅のリビングで、マクロビオティックのお弁当を食べながら、皆さんといろいろ議論をしていました。
 国谷何とも言えない素敵な時間です。
国谷何とも言えない素敵な時間です。
今村荒川さんは、「今村君、人間は死なないんだよ」と言うんです。人間は単人称ではなく複数人称になって、環境と一緒になって作られていく。だから肉体的に滅びても死なない。そういう壮大な転換の哲学を持っていました。だから、建築家は人間を作るための建築を作らなければいけないのに、なんか便利な箱しか作ってないと。ただ機能的で、ご飯が食べやすいとか座りやすいとか、そういうことばかりやっているけれど、本来の建築とはそういうものではないと。
そういった議論の経験が自分の中に残っていて、僕は建築から始めましたけれど、世界の成り立ちとか社会の在り方をずっと考えています。
国谷20代後半から30代に、磯崎新さんや荒川修作さんと出会い、そして荒川さんのお宅では普通では出会えない方々との議論のなかで、自分の考え方や視点というものを養われた。すごく幸せな経験ですね。
今村僕が望んだというよりは、本当にご縁だと思います。だから大学でも、何かを教えるというよりは、学生たちに縁が生まれるような場ときっかけを作ることが、僕の役割だと思っています。
土と空き地が人を育む
今村文化政策とか人を育てたりするときの僕の哲学は「土」なんですけれども、もう一つは「空地」なんです。大学でもどこでも、みんなカリキュラムで埋められている。でも人間って、与えられたことをそのままやるのではなくて、それを理解するためにはそれなりの時間が必要です。だからそこは詰め込んじゃいけない。味噌でいうと発酵させる時間をしっかり作らないと、学べないんです。情報として学ぶんじゃなくて、経験して学ばなきゃいけない。だから空地とか隙間を計画として作ることが大事です。ブランクみたいなものをどう社会や教育のなかに作っていくか。
国谷ブランクというのは、物理的な空間ではなく、時間的なブランクですか?
今村空間も時間も両方です。例えば教室って、すごく目的的じゃないですか。先生が前に立って、みんな同じ方向に並んで座る。そういうのもやめたい。
国谷双方向にするのですか?
今村丸い輪になって座ればいいですよね。もっと言うと、四角い壁は何のためにあるのか? じゃあみんな外へ出ようとういことで、僕はよく外で授業をしています。藝大にはベンチが一個もない。本来だったらニューヨークの公園のようにベンチがあって、座っていたら学生がそこにふらっとやってきて、授業中には聞けないようなことをちょっと聞いてみるとか、そういうふうにして学ぶことっていっぱいあるじゃないですか。
国谷有機的な出会いが起きるような時間と空間ということですね。
今村そういう隙間の時間とか、自由で目的的ではない空間とかを、大学全体は作らなきゃいけないし、そういう社会を作らなきゃいけないと思うんです。近代社会以降、人間は目的的にものを作ろうとしてきたけれど、それをシフトしないといけないと思います。
トーキョーワンダーサイト

国谷藝大に来られる前に今村さんが東京都のトーキョーワンダーサイト*の館長をされていた頃の記事を読みますと、若い世代のサポートの重要性を力説されています。芸術文化行政に携わる中で、若手芸術家支援に最も力を入れていたようですね。
| トーキョーワンダーサイト…2001年に若手アーティストの育成支援機関として開館。アーティストの継続的支援、展覧会やパフォーミングアーツの公演、領域横断的/実験的な試みのサポートなどを行う。2017年にトーキョーアーツアンドスペースに名称変更された。 |
今村2001年に僕が東京都の参与になったとき、東京都は赤字財政再建の真っただ中で、 当時の石原慎太郎都知事はコストカットを行っていました。そんな状況の中で石原さんにお会いする機会があって、「土を育てなきゃいけないんです」と訴えました。僕は当時、私塾をやっていて、公から与えられたものをやるのではなくて、自分たちで何かを起こさなきゃいけないと考えていたんです。それで縁あって一緒に仕事をすることになりました。
学生時代からアーティストの友人はいましたし、卒業するとアトリエもない仕事もないという状況を目の当たりにしてきました。学校の用務員さんをやったり、居酒屋でアルバイトしながら創作を続けるというのを、みんながんばってやっていた。今はだいぶ良くなりましたけれど、2001年頃は貸画廊に何十万も払って個展をやっていていた。DMから何から全部自前なんです。ひどいでしょう? 未来は若い人にあるのに。だからアーティストが活動をしていけるインフラ作り、土づくりを行政がサポートしていかないといけないと思いました。
ワンダーサイトでも若手を選んで自由に展覧会をしてもらったり、そこに批評家を呼んできたりして、支援をしていました。宣伝などは全部我々がやって。アーティストインレジデンスも始めて、世界10都市の芸術機関と提携してアーティストを派遣したり。いい作品ができたから海外に行くという昔ながらのシステムではなくて、やはり今は世界がリンクしている時代ですから、例えばガザで起きていることは、今この世界で起きているんだと、若い人たちは国際的な文脈で課題を考え作品を作ったりしています。若い人たちの活動をサポートすることで、彼らが自分たちでいろいろなものを発見していくと、それが未来のシードになっていくはずです。17年間やったワンダーサイトの館長時代は、何もかもがマネタイズされる時代でしたから、意図的に若い世代を支援する場所を作っていかねばと思っていました。
国谷当時は新自由主義の風が吹いていました。
今村そうですね。何かインベストがあったらリターンがあって、そのリターンが倍々じゃないと許されないという時代でした。僕はそういう結果主義ではなくて、土だ空地だって言って、みんなで回り道をしようと。ある意味社会の流れとは反対でしたけれど、でもいまだにそういう信念を持ち続けています。それがやはり人を作っていくし、未来を作っていく。
- 1
- 2