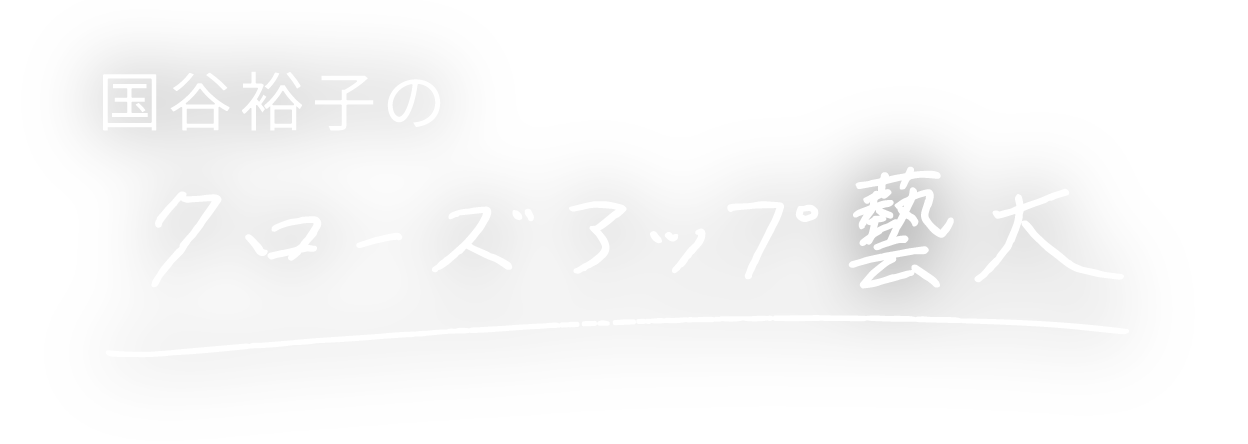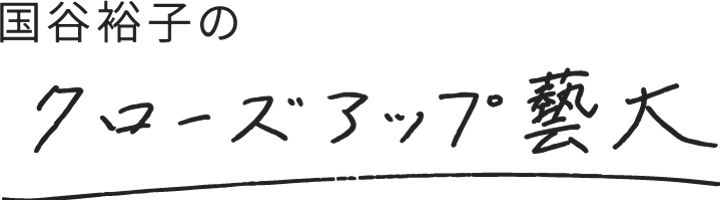第二十回 毛利嘉孝 大学院国際芸術創造研究科教授/未来創造継承センター長
クローズアップ藝大では、国谷裕子理事による教授たちへのインタビューを通じ、藝大をより深く掘り下げていきます。万博体育APP官方网_万博体育manbetx3.0の唯一無二を知り、読者とともに様々にそれぞれに思いを巡らすジャーナリズム。不定期でお届けしています。
>> 過去の「クローズアップ藝大」
>> 「クローズアップ藝大」が本になりました
第二十回は、大学院国際芸術創造研究科教授の毛利嘉孝先生です。専門は社会学やポピュラー音楽研究で、「クリエイティヴ?アーカイヴ」を目指す未来創造継承センターのセンター長も務めています。2024年6月、同センターの附属機関である小泉文夫記念資料室にてお話を伺いました。
【はじめに】
毛利先生がインタビュー場所に選ばれた小泉文夫記念資料室は音楽学部の2階、いくつもの練習室を横目に見ながら歩いた廊下のはずれ、ひっそりとした場所に隠れるようにありました。目立たない入口で靴を脱いでスリッパに履き替え入室すると、そこには国内外30数か国から集められた民族楽器が並べられ、本や雑誌、写真、楽譜、録音や映像資料、民族衣装など世界の伝統芸能、民俗音楽について知ることが出来る実に豊かな空間がありました。
毛利先生は秘境と呼ばれる藝大の中でもここは「秘境の中の秘境」と表現していました。何故、今、未来創造継承センター長を務める毛利先生はこの場所に光を当てたかったのか。2時間に及んだインタビューは、小泉資料室の持つ意義から始まり、現代において芸術とは何か、社会の中におけるアートの役割やアーティストの生き方についても考え、そしてこれからの東京藝術大学のミッションについてまで問いかけるものとなりました。
クリエイティヴ?アーカイヴとは
毛利
今日の僕の最大のミッションは、国谷理事をここ、*小泉文夫記念資料室に連れて来ることでした。
国谷
このような資料室があることを恥ずかしながら全く知りませんでした。
毛利
小泉先生は僕らの世代だとラジオとかテレビに出演されていた印象が強いですね。こういう西洋音楽やポピュラー音楽以外の民族音楽の世界に興味を持つ窓口だったと思います。民族音楽以外でも変わった音楽をやっている人が一回は通った道というか。
小泉資料室はもちろん音楽学部で音楽民族学を研究している人に利用してもらえればいいんですけど、こういうのを面白がる人はそれだけではない気がする。美術学部の学生とか学外の人も、こういうものに触発されて自分で作品や曲を作ったり。
| *小泉文夫記念資料室…日本における民族音楽学の研究者として活躍した故小泉文夫音楽学部前教授(1927-1983)が国内外30数か国でのフィールドワークで収集した録音資料、映像資料、図書、楽器、民族衣装などを保管し、学内外に公開している。 |
国谷
衣装とか映像に触発される人もいるでしょうね。坂本龍一さんも学生時代に大変インスパイアされたと、昨年の展示で紹介されていました。
毛利
大学美術館での展示(2023年11月10~26日「芸術未来研究場展」《クリエイティヴ?アーカイヴ》)では、そういう紹介をさせていただきました。坂本龍一さんご本人によると、音楽学部の授業にはほとんど出なかったけど、小泉先生の授業だけは出ていて、すごく傾倒していたそうです。多分それが後のポップスの活動とか、イエロー?マジック?オーケストラにつながるのかなと、坂本さんの音楽を聴いているとちょっとわかるところがありますね。
藝大というと西洋のクラシック音楽のイメージが強いんですが、小泉先生は唯一無比というか、「世界音楽」とでも呼ぶべき音楽の先駆者だった。
 1971年 アフリカ調査時の小泉文夫(右)(小泉文夫記念資料室所蔵)
1971年 アフリカ調査時の小泉文夫(右)(小泉文夫記念資料室所蔵)
国谷
とてもシンボリックな感じがします。今はダイバーシティ、多様性が重視されていますから。
毛利
小泉先生は藝大の歴代教員の中でもスターの1人ですが、藝大の音楽学部は西洋音楽中心だったということもあって、残念ながら最近は忘れられている感じがします。語り口がすごく上手で、お話も面白かったんですよ。
2022年に新設された未来創造継承センターでは、こういう民族楽器の保存や修復とかも研究のテーマにしたいと話しています。例えば三味線ひとつとっても、猫の皮という素材が使えなくなっているのはよく知られていますが、伝統楽器は職人も減っていて、まさに継承が危ぶまれている。楽器をどう作るとか、楽器を作る職人や道具を作る職人をどう組織化するかとか、そうしたインフラのことは藝大のような大学が考える時期に来ていると思っています。そういうことを言い始めると、何もかもやらなきゃいけないという話になりますが。
国谷
未来創造継承センターは何を目指しているのでしょうか。
毛利
元々はアーカイヴセンター的な位置付けから始まったんだと思います。前任のセンター長の桐野文良先生は美術学部の文化財保存学の先生ですね。けれども、アーカイヴセンターというとどうしても古いものを集めただけの資料室と思われがちです。そうではなくて、むしろそれを活用して、将来の藝大をつくる資源にしていきたい。そうした未来志向で教育なり外部への発信について考えるために、“アーカイヴ”という言葉をあえて使わずに「未来創造継承センター」という名称にしたのだと思います。
藝大にはいろいろな資源があって、多くは美術館とか図書館とかにあるんですが、例えばこういう小泉資料室みたいな、図書館でも美術館でもないものがたくさんある。そういうものをもう少しまとめた形で可視化して、積極的に使って外に見せていこうと。私としては大きな仕事だと思っています。
国谷
ホームページに、「過ぎ去った過去の作品の中に、私たちが未来の可能性の断片を見出すことはよくあること」と書かれています。具体的にはどのような事例がありますか?
毛利
それこそ小泉資料室には、その時に見えていた光景や聞こえてきた音などが集められている。でも、その時には見えていなかったもの、今だからこそ見えてくるものもたくさんあると思うんです。それが、アーカイヴの面白さですね。ここにある資料も、音楽民族学の枠を越えて、ワールドミュージックや他領域と接続したり、インターネット、特にYouTubeなどの普及で別の解釈が可能になる中で、全く違った見え方をしてるんですね。小泉先生も自分が収集したものが将来どのように活用されるかまでは、想定していなかったのではないでしょうか。

センターの中には大学史史料室という組織もあって、藝大の前身の東京音楽学校と東京美術学校の資料をアーカイヴしているんですが、そこからも一つ例を挙げさせてください。
日本の作家や、海外で勉強や作家活動や演奏活動をして藝大に戻ってきた先生とか、藝大を卒業して日本で活躍した日本人のアーティストや演奏家についてはそれなりに研究されているし、歴史も語られている。でも、これまで、その多くはどうしても「日本」中心の歴史観だったんですね。
でも、実際には戦前からの歴史を見ると、たとえば、中国や韓国、あるいは東南アジアの国から来て藝大で学んだ留学生が母国に帰って、のちに重要な作家になったり先生になったりして活躍している例も少なくない。最近では、その国の研究者たちが藝大に資料を探しに来ることが増えています。逆にそうした海外の研究者を通じて、私たちが「そういう留学生が藝大にいたのか!」と再発見する。そうすると、これまでは藝大は「日本」を代表する大学として認識していたのが、アジアの(あるいは「帝国の/宗主国の」)大学として再認識させられるし、そのことで新しくアジアとの関係を作りなおせるかもしれない。それが、過去の資料の中で未来を見つけるということかなと思うんです。
アジアの現代美術が面白くなって来た過程の中で、戦前から戦後へと繋がる歴史における日本とアジアの関係性をどのように考えたらいいのか。そうした観点が近年になってから再発見されている感じがして、そういうことを考えながら書きました。
国谷
つまり、過去のものに違った視点から光を当てることによって、新しいものを創造していくという発想ですね。
毛利
最近の現代美術とか音楽制作はそういう傾向があります。全くゼロから何か新しいものをつくるより、今までの歴史の中から何かを発見してそれを少しずつ組み合わせて新しいものを生み出す。本当にポストモダン的な状況だと思います。藝大はそういう素材も宝庫なんです。
アーカイヴセンターとは言わずに未来創造継承センターとした理由のひとつは、やはり単純に過去の歴史を書くということを目的にしているわけではないからですね。藝大の歴史についてはこれまでも蓄積がそれなりにあるし、藝大100周年を期に『東京芸術大学百年史』を編集した時にかなり掘り起こされている。むしろ今の見方で古い歴史や資料、作品を活用するとか、あるいは今活動している作家や今進んでいるものをこれからどのように歴史化していくか、そういう“今”からもう一回考え直すということが、この名前に込められています。

国谷
その取り組みを続けていくと、藝大に対する見方も変わって来ますね。藝大自身も変わるかもしれません。
毛利
そうだと思います。藝大とは何か、全然違う見方をしなきゃいけない。近代化にあたって西洋の芸術を導入するのと同時に日本のナショナル?アイデンティティを構築したというのが、今までの藝大の見方だけれど、留学生の視点や、アジアとの交流の歴史という視点から見れば、我々が知っている藝大とは違う藝大があると思います。
国谷
美術学部の前身である東京美術学校の成り立ちからすると、日本にはアートとか美術といった概念が無かったけれども、工芸などの技術が発展していて、そこに外からの眼差し、西欧からの眼差しが注がれたことによってアートとして発見されたというプロセスがあったとされてきました。そういった、これまでの藝大の誕生にまつわる捉え方から脱皮しようとしているのでしょうか。
毛利
本当は自分の専門からは遠いんですけれども、あえて乱暴なまとめ方をすると、初期の頃の藝大(東京美術学校?東京音楽学校)の歴史は、ほとんど日本の美術史?音楽史と重ねあわせることができます。美術?音楽の高等教育のほぼ全部が藝大で行われていた。そしてそれと同時に、アジアの歴史でもあるんですよね。先ほどもお話ししましたが、アジア各国からの留学生もいたし、台湾や中国大陸、朝鮮半島も含めて日本の植民地だった地域もある。現在の「北は北海道から南は九州?沖縄まで」というのとは異なる空間感覚を持っていたはずです。それが今になって見えてきたのではないでしょうか。もちろんそこには人文学におけるポストコロニアリズムとか脱帝国主義の運動とか、あるいは西洋中心主義に対する非西洋的な起源の再発見とか、いろいろあると思うんですけど、やっとダイバーシティとか藝大の中にそもそも存在していた複雑で重層的な歴史がここに来て見えてきた。小泉資料室は、その一つの核だと思うんです。
“縦割り”は20年経っても変わらない
国谷
藝大自身が今、変わらなくてはいけない時期に来ていると思われますか?
毛利
はい、やはり転機に来ていると思います。僕は2005年に音楽学部の音楽環境創造科の教員として入ったわけですが、藝大というのは音楽も美術も非常にクラシックで、こんなに古臭いのかと率直に思いましたし、その感覚は今もあんまり変わっていない。大きく変化しているところもあるけど、全体としてはほとんど変わっていないと思います。やっぱり変われるなら変わった方がいいところがたくさんある。その一方で面白い資源も人もいっぱいあるんですね。使えるものを使い切れていない。それを使いこなしてちゃんと変われば、まだまだ可能性はあると思います。
国谷
毛利先生は京都大学の経済学部で学び、卒業後は広告会社の社員としていろいろな音楽の企画をなさって、そこからロンドン大学に行き社会学者になられた。いわゆるアーティストではないですよね。
毛利
芸術については全く才能がない(笑)。藝大に就職するまでは本当に秘境だと思っていました。
国谷
どういうふうに秘境だと思っていたのですか?
毛利
敷居が高かったですよね(笑)。僕の専門の領域は、文化社会学とかカルチュラルスタディーズ(文化研究)ですが、研究対象は基本的にポピュラーカルチャー。音楽というとロック、パンク、ジャズとか、せいぜいある種の実験音楽やサウンドアートだし、美術も多少現代美術は研究対象にしているけど、それでも絵画や彫刻じゃなくてワークショップとかアクティヴィズムとか、あるいはもうちょっとデザイン寄りのものを対象としていましたし。
国谷
アートの教育に携わってほしいと、あえてアーティストではない方を藝大は招き入れたわけです。ですから当時の藝大は外からどう見えていて、そしてこの20年近くの間に藝大はどう変わったのか、あるいは変わらなかったのか、ぜひお聞きしたい。
毛利
とはいえ、さっきの発言はやや訂正した方がいいかもしれないですね。変わった部分もあります。組織でいうと、取手で美術学部先端芸術表現科はすでに新しいことを始めていたし、横浜では大学院映像研究科ができました。僕が最初に配属された音楽学部の音楽環境創造科も設立したばかりで、取手にありました。そこでは結構新しいことをやっている自負もあったんですけれど、率直に言うと、あくまでも音楽環境創造科という枠組みだけで「こういう大学にしよう」とかはあまり考えていませんでした。自分の研究室の学生たちと面白いことをやるという意味では、藝大はけっこう自由にいろいろなことができる大学なんですよね。ただ、藝大全体がそういうわけではなくて、やっぱり全体としては旧来の美術、音楽の枠組みの中で、お互いにあまり交流がないままやっていて。僕は音楽も美術もどちらも素人で、逆にどちらとも付き合いがあるから、「なんでこの人たちはお互いにこんなにしゃべらないのだろうか?」と。それは今でも思っています。
未来創造継承センターの仕事でいろいろな所属の先生方と話す機会も増えて、「ああ、こういうことなのか」と。一言でいえば、縦割りってことですね。と言いますか、「大学が縦割り」という話、記事になりますか(笑)。
国谷
組織が縦割りだという話は企業の方々もよくします。経営者にインタビューをすると、なぜイノベーションが生まれないのかという文脈の中で、企業風土をどうやって変えるか、縦割りの組織にどうすれば横串を通せるのか、皆さん同じような悩みを抱えています。
毛利
“棲み分け”と言えば聞こえはいいですけど、やはり専門性が高いから縦割り社会にならざるを得ない。美術の先生が音楽のことに口を出さないのは、やっぱり音楽には音楽の専門性があるし、そこでのしきたりというか、そこで成立している世界があるから。それは美術の中でも、音楽の中でもそうですね。
学生の中には、その道ひと筋で子供の時から専門的な訓練をして、ある種人生を捧げてきた人がたくさんいます。彼ら、彼女たちに何か他のことを言うのはどうかと考えてしまう。でも、それ自体がひょっとすると日本の教育の一つの問題かもしれません。留学をしたから思うんですけれど、海外の大学やアートスクールだと専門家にもいろいろなことをやらせようとしますよね。必ずしも一つのことだけではなくて。
国谷
特に今はそうですよね。
毛利
恐らくそうした教育のカリキュラムをなかなか作れなかったんだと思います。
社会人と藝大生が一緒に学ぶ
国谷
藝大の「クリエイティヴ?アーカイヴ」を考える軸としては、過去の中から未来の新しいものを生み出すという時間軸ももちろん大事ですが、一方で、企業、自治体、NPOなどの多様な外部のステークホルダーとの横軸の連携が重要だともおっしゃっています。藝大の枠を超えた広がりを作りたいという、強い意欲を感じます。

毛利
意欲が空回りしないといいんですけどね(笑)。
ちょうど今、* 有楽町アートアーバニズム「YAU(ヤウ)」で、社会人と学生が一緒に学ぶという授業をやっています。やはり外部の力はすごく大きいから、藝大が変わるきっかけになるんじゃないかな。企業に迎合するわけではなくて、内在的に変われるかなと。
僕が担当しているのはアーカイヴを活用する授業なんですけれど、アート=ベイスド?リサーチ(Arts-Based Research)と呼ばれているようなことをやろうとしています。わかりやすく言うと、写真とか映像とか音とかを使って調査をして、アウトプットにもそうした手法を使う。都市計画とか社会学、人類学、経済学なんかでもすごく使われている研究調査です。
例えば、小泉先生が書かれた本はすごく面白いんですけれども、何より面白いのは映像とか音とかなんですよね。これだけ世界が複雑だと、細かく書かれた100ページの企画書より、1分の映像の方が伝わることもたくさんある。藝大にはそういうノウハウがあるし、藝大生の中にはアーティストも研究者もいますからね。
アートの範囲が広がると、ビジネスをしている人ともっと相互乗り入れできるような領域ができるかなと思います。今はまだ始めて3、4回なのであまり大きなことは言えないですけれど、感触としてはいいです。みなさん非常に積極的に参加しています。
| *有楽町アートアーバニズム「YAU(ヤウ) 」…有楽町アートアーバニズム実行委員会(NPO法人大丸有エリアマネジメント協会、一般社団法人大手町?丸の内?有楽町地区まちづくり協議会、三菱地所株式会社により組成)が2022年に立ち上げた、街がアートとともにイノベーティブな原動力を生み出す、実証パイロットプログラム。2024年より社会人と藝大生が有楽町で共に学び合う社会共創科目(公開授業)を展開している。 【参考】>> 人材育成プログラムの実施に向けた連携協定を締結 |
国谷
藝大のオフキャンパスみたいな位置づけで、藝大の学生も受講できるし、学外の人たちも受けられるのですね。
毛利
そうですね。有楽町で開講していて、学生は基本的にオンラインで、社会人はオンラインまたは対面で受けます。全体で80人ぐらいですね。最後に何かアウトプットをしようと思っています。
国谷
社会人の方々はどういう目的で受講されているのですか?
毛利
まだはっきりわからないですけど、やっぱりアートに何かあると思っている人が多いし、プレゼンテーションとか調査研究みたいなことを、今までとは違うやり方でやりたいと思っているようです。
企業の枠組みの中で考えるといろいろとクリエイティヴィティに限界があると思うんですよ。でもアーティストってぶっ飛んでいるので、変なこととか、訳の分からないこととか、できもしないことを言ったりする。そういう発想がいろんなヒントになるだろうし、実践すること自体が、何か新しい議論のきっかけになるんじゃないかと。
これからの日本は、アートと一緒にビジネスをつくるようなところが一番熱い気がします。これもあんまり根拠はないんですけれども、すでに熱気としてはすごく感じます。
国谷
そうですね。STEM(science, technology, engineering and mathematics)教育だとか、それにARTが加わって今やSTEAMが大事だと経済界の方々が強調されています。
毛利
もちろんある種の流行りかもしれないので、そこは疑ってかかる必要はあるけれども、何か具体的な成果が出ると一気に情況が変わると思います。
後期はワークショップを予定していて、公立はこだて未来大学の准教授の島影圭佑さんという人をゲストに迎えます。彼はエンジニアなんですけれども、お父さんの目が悪くなくなって、本が読みづらくなった。それを解消するために《OTON GLASS》という、本を見ると文字を自動的に読み取って音声化してくれる眼鏡をつくった人なんです。
国谷
とても思いつけない、素晴らしい発想です。
毛利
技術的にはそんなに難しくないのかもしれないけど、眼鏡にするというのがアーティストっぽいなと思うんですよね。
今の20代、30代の作家ってそういう、既存のアートの枠では捉えられない“その他”の人が増えています。アートなのかって言われるとそうでもないし、デザインなのかと言われるとそうでもなくて、その間みたいな。藝大でも“その他”の人が一番面白くなってきている気がします。
国谷
企業の方々にも最近はアートの大切さが少しずつ認識されていると思いますが、毛利先生は「新しい職能に求められるのは、創造力や独自性、コミュニケーション能力、アーティストに求められる能力と、限りなく似ている。多くの人が多様なアイデンティティを保ちながらアーティストのように生きることを強いられる」と書かれています。それは、アーティストに対する評価が高まっている、つまり藝大生の活躍の場が広がっているということなのでしょうか。
毛利
そうだといいんですけれどもね。「アーティストのように生きることを強いられる」というのは、大変な時代だというネガティブな意味も入っています。今では、一般企業の会社員でもコミュニケーション力とかプレゼン力、クリエイティヴ力とかをすごく求められるし、それは結構ストレスだと思う。でもそうなった以上は、アーティストがどんどん社会に出て働けばいいと思うんですよね。昔は企業に入ったら朝9時から5時まで同じ仕事をやってみたいなイメージだったけれど、今はそんな仕事はすごく減っていて、もっと自由に時間を使えるいろんな仕事があります。
僕は20代で広告会社にいて、大変だったけど面白かったこともたくさんあった。むしろ藝大とかで勉強した人の方ができることがたくさんあるのにと、そのときも思っていました。社会のほうが寛容になった方がいいと思うし、学生の方もちょっと面白い仕事をしてみるというか、ビジネス自体をアート化するみたいな。海外で成功しているIT系の人たちって、やっぱり非常にアート思考で、アーティストみたい人もたくさんいるし、プレゼンテーション力しかないような人もいる。

国谷
だからYAUのような場に、企業の方が積極的に一歩を踏み出してきているのですね。藝大への憧れもあるかもしれないですけれど。
毛利
秘境を覗いてみたいんですよね。それは間違いなくある。
国谷
そして藝大生も、大学にいたら絶対に接点がないような人たちと会い、外の世界とつながることができますね。
毛利
循環していきますよね。
アートの枠を超えた“その他”の人たちが中心になっていく
国谷
つながることによって、アーティストの活躍できる範囲が広がっていきます。
毛利
そうですね。もちろんそういう場が広がるのはいいことなんですけど、僕がそもそもアーティストではないので、藝大の僕の研究室の学生は僕みたいな人が多くて、“その他”みたいな学生が集まるんです。僕は一般大学でも授業を担当しているんですけれど、みんな4月、5月ぐらいからスーツを着て就活に追われる。でも藝大の僕の学生はほとんどそんなことしないんです。かといってアーティストになるわけでもなくて、自分たちで何かを始めたりする。オルタナティブ?ライフみたいなのを追求する人が多い。
そのタフさたるやちょっと面白いと思っていて、むしろそうした人たちが次のシーンをつくっていくと思うんですよ。インキュベーターというか、新しい何かを創造して、自分で会社をつくったり、場合によっては大きい会社を飲み込んでしまうかもしれない。そういう人たちが中心になっていく未来を妄想しています。
経済自体もずいぶん変化して、緩くなりました、昔は系列化されていて、メーカーでも金融でも大手企業に行かないと話にならない感じがあった。だけど、今のITとかソフトウェア開発とかコンテンツ制作とかは、そういう産業では全くなくて、ひとりでも友達同士でも始められるし、しかも成功したらそれまでのビジネスモデルを変える可能性もある。むしろ大企業にいるほうがいざという時に「つぶし」が効かなくてリスクが高まってる。
国谷
藝大出身の方のそういう成功物語をもっと知りたいです。リンクを貼っていただければ、皆さん、見に行きたいのでは。
毛利
例えば、僕の研究室出身ではないけれど音楽環境創造科の卒業生だと、福嶋麻衣子さん(もふくちゃん)というアイドルプロデューサーがいます。テレビでコメンテーターとかもしているから、知っている人もいるかもしれません。ライブハウス経営とか音楽プロデュースとかって今までは産業の中心じゃないと思われていた。でも、今となってはそういう周縁にこそいろいろな産業が生まれていると思うし、ある意味脱線して小さなビジネスをやってる人の方が発展性があるかもしれない。
僕の研究室の出身者が千住校地の近くで古着屋さんをやっていて、Tシャツ1枚数万円で売るようなニッチなヴィンテージの商品を扱っているんですけれども、すごくセンスがよくて成功していて、最近では大阪にもビジネスを広げています。古着屋ビジネスなんて昔は趣味の世界だと思われていましたが、今やファッション産業の中でも大きな軸の一つになっています。
そういう人の特徴は、もちろん大企業には頼らないし、藝大にも頼らない。独立してやっている。美術の中でも現代美術とか、音楽でもどっちかというとポップスに近いような世界とか、あるいはデジタル、ゲームとか、映像制作とかそういう新しいクリエイティヴ産業ですよね。その辺は実はすでにそれなりにいろんな人が活躍していますが、今はまだ主流の産業だと思われていないし、アートの中でもまだまだ周縁なので、なかなか目立たないんですよね。
- 1
- 2