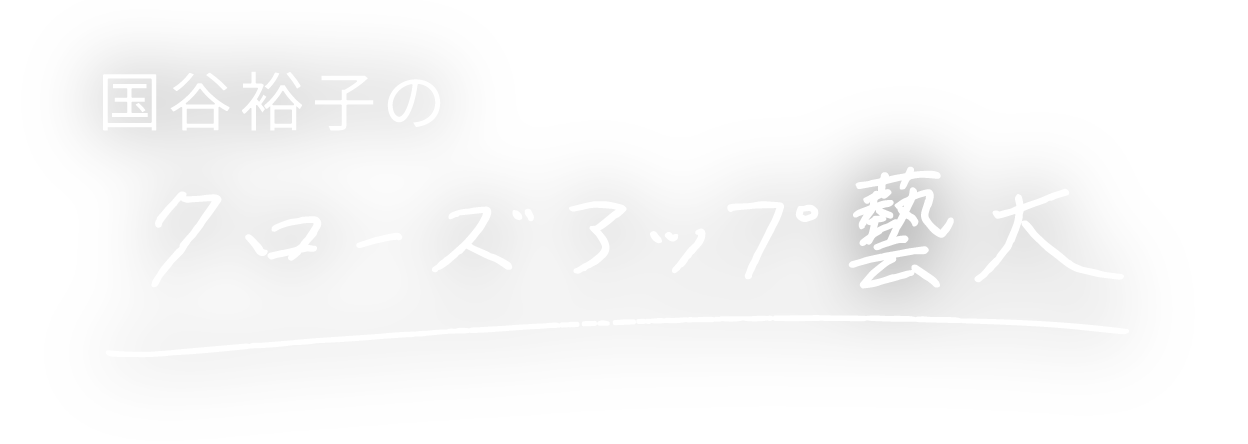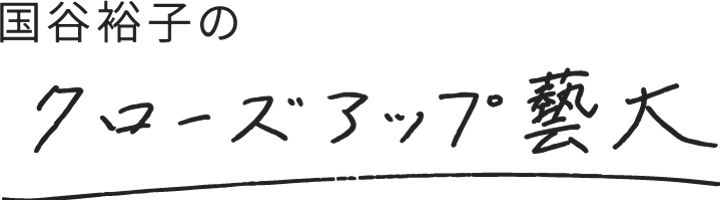第十七回 薄久保香 美術学部絵画科准教授
クローズアップ藝大では、国谷裕子理事による教授たちへのインタビューを通じ、藝大をより深く掘り下げていきます。万博体育APP官方网_万博体育manbetx3.0の唯一無二を知り、読者とともに様々にそれぞれに思いを巡らすジャーナリズム。月に一回のペースでお届けします。
>> 過去の「クローズアップ藝大」
>> 「クローズアップ藝大」が本になりました
第十七回は、美術学部絵画科准教授の薄久保香先生。本学の大学院美術研究科絵画専攻油画の博士後期課程を修了後、現代美術作家としての活動を開始し、2020年度より油画の教員として赴任されました。2022年3月、大学美術館陳列館にてお話を伺いました。
【はじめに】
大学美術館陳列館の2階、天井に近い窓から優しい光が注ぎ込んでいました。すらりと背の高い薄久保先生は「アトリエにしたいような空間ですね」と見渡しながらおっしゃっていました。
今では国内外で活躍されていますが、アーティストという職業に対してリアリティを持つまで時間がかかり、今もってアーティストが自分の職業なのか問いかけているそうです。
バーチャルとリアルの問題を見つめる薄久保先生のアートに対する考え方はどのような思考回路で生まれてくるのかお聞きしました。
自分で考えなきゃいけないことに気づいた
国谷
今は教えることと研究?制作と、どちらが中心になっていますか?
薄久保私は20代の頃から作家業を続けていまして、それが中心軸なんですけれども、10年前から非常勤講師という形で大学生たちと関わらせていただいて、ちょうど2年前にこちらの専任になりました。今のバランスは、どちらも重要な2本の柱だと思っています。
国谷
京都と東京の二か所に拠点を置かれているのですね。
薄久保
メインの制作は京都のスタジオで行っています。私の夫(大庭大介)も画家で、京都芸術大学で教員をしています。東京藝術大学の大学院時代の同級生なんです。ちょうど今開催されている清水寺の展示(『ARTISTS’ FAIR KYOTO 2022』2022年3月5日?13日)では作品の位置が隣同士で(笑)。あんまりそういうふうに並ぶことはないんですけれど…。
国谷
ぜひ拝見したいです。
薄久保先生は東京造形大学造形学部美術研究科絵画専攻を卒業されて、その後、東京藝術大学大学院美術研究科を修了されました。東京造形大学ではどのような能力が身についたと思いますか?
薄久保
大学ではもっといろいろ教わるんだろうとイメージしていたんですが、入ってみるとすごく主体性に任されていました。藝大もそうですけれど、多くの日本の美術系大学におけるカテゴリーとしての油画とか絵画というのは、 “現代アート領域”という認識を含んでいます。入学試験にペインティングの実技はありますが、絵画はあくまで多様な表現の為の起点なんです。だから入学後にさまざまなメディアの可能性が一気に広がって、映像、インスタレーション、パフォーマンス、全部ありなんだ!って驚きました。

その中で私も写真とか映像メディアとかいろいろやってみたんですね。ペインティングを腰を据えてやろうと思ったのは大学3年ぐらいのときで、それも自己流の模索の中から作品を描いていって、書籍などで調べたり、自問自答しながらテクニックを身につけていった感じです。
あとはやっぱり同級生とか同世代のアーティストとの出会いが大きかったですね。彼らと話したこと、一緒に考えたことが自分を成長させてくれたと思います。
国谷
絵画のテクニックを教わるのかと思っていたらそうではなくて、いろんなメディアがありますよ、どうぞご自由にトライしてくださいと。いろんなトライをしながら主体的に選びなさいと。友達や他の学生たちとのディスカッションや自問自答を繰り返す場所だったのですね。
薄久保
そうですね。主体的に自分で考えなきゃいけないということに気づいたんだと思います。それはやっぱり重要なことです。アートというのは世の中に山と積まれている物事から、まだ課題かどうかもわからないようなものを抽出して、それに対して何かアクションをし続けることだと考えています。だから人から課題をもらう時点で矛盾しているんですよね。与えられた課題をやっているうちは、まだそれはアートというか、表現に至っていない。そういうことがだんだん腑に落ちて行きました。
国谷
自分が何に引っかかりを持って、そこから何を創造の種にしていくか。徹底的に自分と向き合うということですよね。そして自分と向き合っている自分も客観的に見て、他人がそれをどう見ているのもまた見る。
薄久保
それはすごくあります。そんな繰り返しのなかで魂が耕されていっていると感じましたね。
国谷
それは今の日本で一番欠けていることかなと思います。自分で課題を考える、自分がどう思うのか、どう捉えているのかを徹底的に考える。現在はそういうことを考える余裕もなく情報に振り回されて、生きるためには目の前のことに対処し続けなければならいない社会が人びとを覆っている。そう考えると、薄久保さんは東京造形大学で美術教育のすごく大事なところを教えられたのではないでしょうか。
薄久保
そうですね。東京造形大学は神奈川県と東京都の境目あたりにあって、もちろん展覧会とかは都内に出ればすぐ見られるんですけれども、誘惑されるような娯楽が無いぶん、すごく生活がシンプルでした。山の中でゆっくりじっくり考えたり、筍を採ったり、友達と料理をしたり、話したり…。今の生活と比べると生きている間には取り戻せないくらい、贅沢に使える時間があったと感じます。
ゲーム会社でCGデザイナーになるも…
国谷
今は入試期間ですが入試が終わると卒業式で、学生たちが巣立っていきます。薄久保先生は東京造形大学を卒業されていますけれど、卒業するときには画家という職業にリアリティを持てなかったそうですね。今では世界各地で個展をなさるような現代美術作家ですけれども、卒業するときにはリアリティが持てなかった。それはなぜでしょう?
薄久保
作家といってもいろんな在り方があると思うんですね。資格を有するような職業ではないし、ハードルを低く設けて自分が作家だと称すれば作家になれる。そういう意味ではすごく近くに感じられるものだとも思います。でもそのときの私は、作家というのは仕事なのか生き方なのか、それをどういうふうに定義すればよいのかも曖昧な状態だったんです。それで、一度会社員になりました。自分が体得した技術をデザインやエンターテインメントの中でいかすのもひとつの生き方かなと。いろいろ模索していたんだと思います。
国谷
学んだ技術をいかせる場所を探してゲーム会社に就職されました。
薄久保
まずは就職先を探すところからでした。大学の就職課に相談したら、ファインアート系の学生でも募集があるところを教えてくれたんです。その中にゲーム会社もあって。
国谷
CGのデザイナーになったんですよね。アーティストと企業に勤めるCGデザイナーって、落差があるようにも感じます。藝大の学生は、就職する人は少なく、「アーティストとしてがんばって一人立ちするんだ!」という気持ちで卒業していく人が多い。
薄久保
その時点で覚悟が決まっている人に対して、純粋にすごいなと思っていました。私はそういう揺るぎない精神とはほど遠くて、今の私だけを見るとすごく順当に進んで来ているように見えるかもしれないけれど、いつも迷って模索していろんなところにぶつかって、失敗もしています。就職したのも、自立しなければいけないという切実な問題に直面して、CGで何か作る仕事も面白いかなって。いろんな技法とかテクニックに、デジタル?アナログ問わず興味があったので、新しいことに挑戦できるかなと思ったんです。
国谷
でも、その会社を1年足らずでお辞めになります。
薄久保
そうなんですよ(笑)。本当に矛盾ばかりの人生なので、学生に偉そうなことを言えるような立場ではないんですけど、反面教師というか人生のサンプルとしては人間らしい部分もあるのかなと。会社で一生懸命スキルを磨いて、プロジェクトチームに入って頑張ろうと思っていたんですけれど、これがまた不思議なことに、自分の制作をいったん休止したことによってやりたいことが見えてきたんですね。
中途半端にはできなかったので、会社で働いている期間、制作は一切しませんでした。会社では3Dの仕事をしていたんですが、新しい技術に触れたときにその後の核となる制作のイメージと結びついたんですね。ペインティングという太古からあるベーシックな表現と、CGの中で視覚的には非常にリアルに表出しているけれど質量を一切伴っていない、光と視覚の中だけに発生するリアリティみたいなことについて考えていて。それでものすごく自分の制作をしたいという気持ちに駆られたんです。ただ会社も好きだったし…。社会人という観点からは、かなり自分勝手な人間だったかもしれませんね(笑)。
国谷
私も最初に就職したところは10ヶ月くらいで辞めてしまったので(笑)。
薄久保
この環境に慣れてしまって戻れなくなるのが怖いという部分もあって、今やらないとタイミングを逃すかもしれないと。それで会社を半年ちょっとで退職しました。でもまだまだ自分ひとりでやっていくには知識も足りないし力不足だと思って、藝大の大学院美術研究科絵画専攻油画に進みました。

国谷
藝大ではどんなことを研究されていたのですか?
薄久保
研究と制作は私のなかではボーダーレスで、研究というと本を読むとか論文を書くというほうによっちゃうと思うんですけれど、制作も研究という。
国谷
制作しながら自分を研究するという感じですか?
薄久保
そうですね。私の場合は制作プロセスにおいて、写真を撮ったりCGを制作したりいろいろな課題があったので、それをひとつひとつ丁寧に客観的に考えていきました。出だしの1年間は何を表現すればいいのかわからなくて模索していて、修士2年になった時に、CGのバーチャルなイメージと実際の出来事を融合したイメージを絵画にすることで納得して、ひとつその段階に達することができました。
国谷
大学院は修士?博士あわせて5年間ですか? かなり長いですよね。
薄久保
そうですね。そんなに行ったかなという感じですけれども。本当に毎日通いましたね。特に博士に進学してからは、土日関係なく上野のアトリエに通っていました。フルに藝大を利用させてもらいました。
バーチャルとリアリティの間で
国谷
大学院では自立的な勉強をしていくわけですよね。藝大に来てからはどんなことを学ばれましたか?
薄久保
学部生の頃は、自分で考えなければいけないということを発見する段階でした。それが大学院で磨き上げられた感じがします。夫も含めて同級生の存在は大きかったですね。
2000年代は日本のアートシーンは、特に若手への注目が集まっていた時代でもありました。日本の文化的表現をグローバルなステージで概念化させることに成功した村上隆さんや奈良美智さんなど、特異点となったアーティストが、我々にも大きな影響を与えて、次世代を考えていく大きな指標になったと思います。商業だけでなく学術的な価値を作っていくコマーシャルギャラリーでも、若手が発表したり所属したりするチャンスがひらかれた新しい時代で、そういうことを一気に取り込んでいったのが大学院時代でした。たくさん展示を見に行って、現状に対してポジティブに感じていることも課題に思っていることも学生同士で話したし、同時代に活躍するアーティストの表現に対し、自分たちが次にどんな可能性を提示できるのかということも考えていました。
国谷
薄久保さんが大学院に通われているときは、そういう時代だったのですね。

薄久保
私の中では、世界とか社会に対してアーティストがどういう問題提起をしていくかという大きな課題と、ゲーム会社で働いたことによって得たもうひとつ明確な課題がありました。それは、スマホを通して観るような視覚的なリアリティ、フラットな光の中で認識しているリアリティと、絵画も人間もそうなんですけど、肉体とか物質という非常に不自由なものをまとっているもの、その間のギャップというかその存在は何なのかという課題で、「これだ!」と感じました。そういう意味ではゲーム会社との出会いは偶然とは思えないですね。そこで得たものは今も制作の糧になっています。
バーチャルとリアリティの間で何が起きているのかということについては、2000年代から今日まで多くのアーティストが課題にしていて、社会学でも考えられてきたし、特種な課題ではないんです。でも自分で自信を持ってGOを出せる課題だということが重要でした。当時はまだバーチャルなのかリアリティなのかみたいな二元論でしたが、今はそうじゃなくて非常にシームレスです。
国谷
曖昧になってきている。ブレンドインしていますよね。
薄久保
はい。それぞれのリアリティがあるし、きっと加速して境界がなくなるんじゃないかというのは2000年代にゲーム会社で働いていたときから考えていたことでした。
国谷
お話を伺っていると、2000年代は価値観の違いを認め合い、チャレンジするアーティストを広く受け止める、非常に開かれた土壌が社会にあったように感じます。その一方で、ギャラリーでの展示において男性に比べて女性アーティストの作品が少ないとか、アートシーンで認められる機会は男女平等ではないという話を聞くこともあります。
薄久保
私は自分が女性だから展示してもらえないとか、そういう経験はなかったのですが、ジェンダーの問題として考えなければいけないようなケースもありますね。確かに海外と比べると日本のほうが子育て期間中に活動をしにくい空気はあるのかなと思います。私は子育てをしていないのでリアリティを持って言えないんですけれど。海外だといい意味で神経質じゃないというか、ギャラリーにも子どもや赤ちゃんが普通にいますけれど、日本ではあまり見かけませんよね。お互いにすごく気を遣っている感じがします。気遣いのハードルを下げるというのも解決策のひとつなのかなと思います。
国谷
薄久保さんは海外でもすごく早くに認められました。
薄久保
大学院を修了する少し前に、バーチャルとリアリティの問題をどのように考えていくのかをテーマにした作品がひとつ形になって、それをきっかけにギャラリーから声がかかり本格的に作家活動を始めました。実はそれまでは全く個展をやったことがなかったんです。学生時代から外で展示をする人はいますけれど、私にはそれが難しいというか、納得していないと誰にも見せられない、みたいな頑固なところがあって。
2008年に東京のギャラリー経由で海外のフェアに出展させていただいて、そのフェアのコミッショナーの一員だったベルリンのギャラリーに今も所属しています。そこで展示?発表するようになって十何年のお付き合いですね。
国谷
ギャラリーでアーティストとして扱ってもらえるようになった。その関係性ができたから、大学卒業時にはリアリティを持てなかったアーティストという職業にリアリティを持てるようになったのでしょうか?
薄久保
これも私の中で矛盾しているんですけれど、アーティストとして活動していけることは非常にありがたいことで、これが仕事なんだって客観的には理解できる。でも、これが職業かと言われると、うなずけない部分もあるんですよね。
国谷
職業か、というのはどういう意味ですか?
薄久保
作品は学術的価値やその作家の思想、「美」としての価値もありますし、一方で売買して取引される以上は商品という面もあります。自分の考えに対して共感してもらえるのはすごくうれしかったけれど、思想を優先にしているがゆえに、こんなことがずっと続くわけない、安定した収入を得られるはずがないという覚悟のような考えもありました。実際に制作と収入が結び付かずに苦労もしました。制作を続けていくと新しい課題も見えてくるし、チャレンジも必要だし、同じものは作れないし、理解されないものも出てくる。そういったことは職業という認識とはすごくズレている感じがしました。でも私にはそのズレをどうすることもできなくて、これは職業なのかということは今も考えていますし、学生との関わりの中でも、これはけっこう重要な部分です。
- 1
- 2